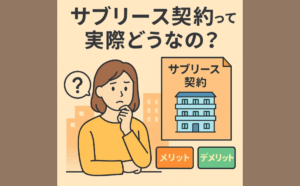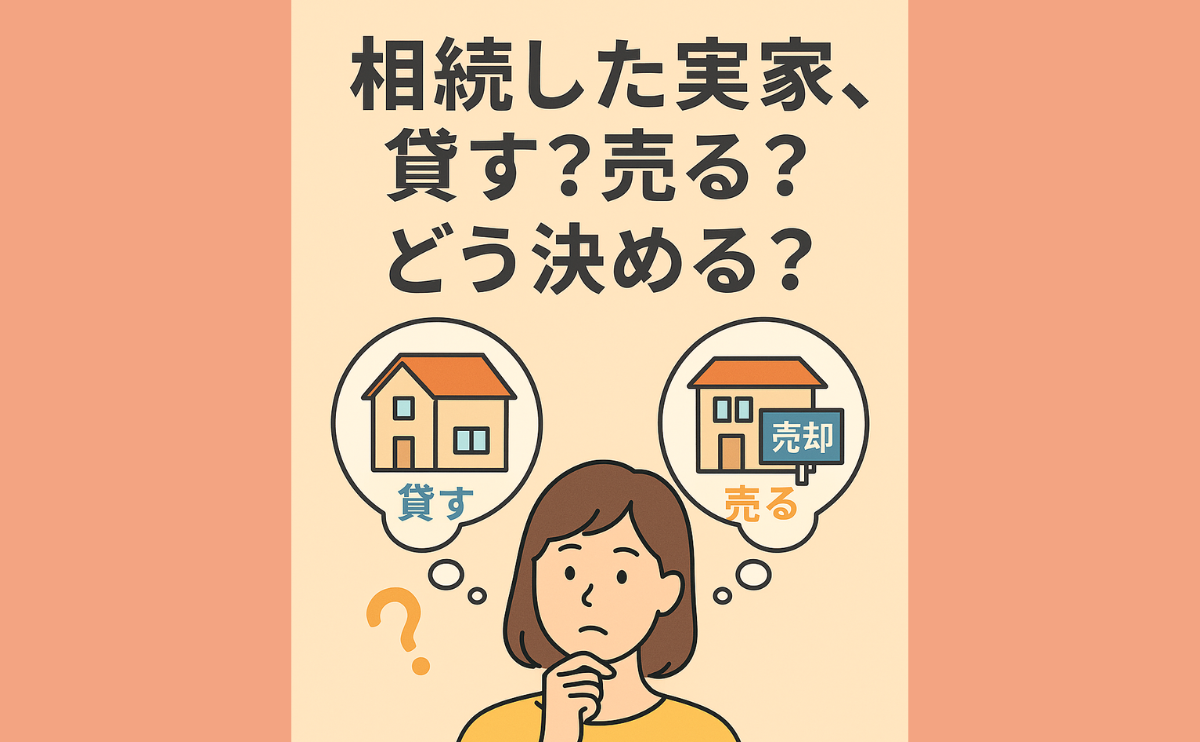
親が住んでいた家を相続した──。
・思い出があるから手放しにくい
・でも空き家のままでは固定費がかさむ
・貸すにしても管理が心配……
こうした葛藤を抱えるご相談は、年々増えています。
今回は 「貸す」「売る」それぞれのメリット・デメリット を整理し、判断のポイントを具体的に解説します。
📌 現状分析からスタート
1.立地と賃貸需要
・駅距離・周辺人口・商業施設などをリサーチ
・SUUMO/HOME’S で近隣の成約賃料・空室率をチェック
2.築年数・建物コンディション
・築25年以上は主要設備(給湯器・屋根・外壁)が更新時期
・耐震基準(1981年以降かどうか)も確認ポイント
3.固定費の把握
| 項目 | 年間目安 | 備考 |
| 固定資産税・都市計画税 | 10~30万円 | エリアによる |
| 火災保険 | 2~4万円 | 加入必須 |
| 庭木・除草・見回り | 2~5万円 | 空き家だと増える |
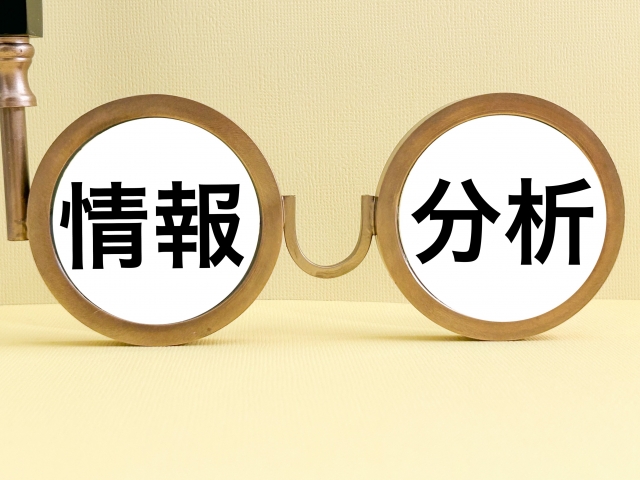
📊 貸す場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 収益面 | 家賃収入で固定費を賄える | 空室・滞納リスク/家賃下落 |
| 感情面 | 思い出の家を残せる | 入居者トラブルへの対応 |
| 税務面 | 減価償却で所得圧縮可 | 青色申告など事務負担 |
| 相続面 | 将来売却時に長期譲渡税率(20.315%) | 相続人が複数だと共有トラブル |
シミュレーション例(築30年 4LDK・家賃10万円の場合)
年間家賃:120万円
− 管理料(8%):▲9.6万円
− 固定資産税:▲15万円
− 空室1か月:▲10万円
= 手残り約85万円(※修繕費別途)

💰 売る場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 収益面 | まとまった現金化・納税資金確保 | 売却益に譲渡所得税・住民税 |
| 感情面 | 維持管理の手間がゼロ | 思い出の家を手放す寂しさ |
| 税務面 | 「空き家特例」適用なら3,000万円控除 | 要件を満たさないと高税負担 |
| 市場面 | 市況が良ければ高値で売却できる 可能性がある | 築古・駅遠などは売れ残る リスクがある |
✔ 売却時の税務ポイント
- 取得費加算の特例:相続税を取得費に上乗せ
- 空き家譲渡の3,000万円控除:
- 一人暮らしだった親の旧宅
- 相続後3年以内に売却
- 1981年新耐震基準へ適合 など要件あり

🏠 判断のフローチャート
✅ ステップ①:家族が将来住む予定は?
- YES ⇒ 「貸す」or「賃貸しながら将来住む」などの選択肢を検討
- NO ⇒ ステップ②へ進む
✅ ステップ②:立地や築年数から賃貸需要が見込める?
- YES ⇒ 家賃収入が固定費を上回るなら「貸す」方が有利
- NO ⇒ ステップ③へ進む
✅ステップ③:売却価格から手取り金額をシミュレーション
- 売却後の手残り(売却価格-譲渡税など)と、
保有時の家賃収入の10年分を比べて判断
- 手残りが大きい ⇒ 「売る」方が合理的
- 手残りが少ない ⇒ 更地活用や他の選択肢(駐車場など)を検討

🔑 決める前に必ずやるべき3ステップ
1.プロに査定を依頼(売買2社・賃貸2社の比較)
2.修繕見積りを取得(外壁・設備の更新費)
3.家族会議で意向確認(共有名義リスクを回避)

✅ まとめ|感情×数字×将来ビジョンで総合判断を
実家には思い出が詰まっています。
しかし「感情」だけで残すと、管理コストや相続トラブルで将来の負担になることも。
- 数字(収支・税負担)
- 感情(思い入れ・家族の意向)
- 将来ビジョン(住む?活用?手放す?)
この3点を並べ、総合点が高い選択肢を選ぶのが後悔しないコツです。
💡 迷ったら、宅建士・税理士・FPなど第三者の意見も参考に。専門家に相談することで、思わぬ選択肢が見えることもあります。
🔜 次回予告|第10回「FP目線で見る!『もうやめたい』賃貸経営の出口戦略」
「築古で修繕費が重い」「管理が大変」──賃貸経営をやめるタイミングは?
最終回は、売却・持ち続ける・建替えなど出口戦略をFPの視点で整理します。お楽しみに!
| 📚 連載記事一覧はこちら! \ 不動産賃貸の始め方がわかる!10の基礎テーマをFPが解説 / 第1回|賃貸経営って本当に儲かるの? 第2回|賃貸経営の収支シミュレーションってどうやるの? 第3回|「アパート建てませんか?」その提案、すぐ乗って大丈夫? 第4回|確定申告、青色と白色って何が違うの? 第5回|空室が心配…まず何から見直す? 第6回|「子どもに不動産を残したい」その前に 第7回|法人化した方が得?個人との違いをざっくり解説 第8回|サブリース契約って実際どうなの? 第9回|相続した実家、貸す?売る?どう決める?(この記事) 第10回|FP目線で見る!「もうやめたい」賃貸経営の出口戦略 |

-min.jpg)