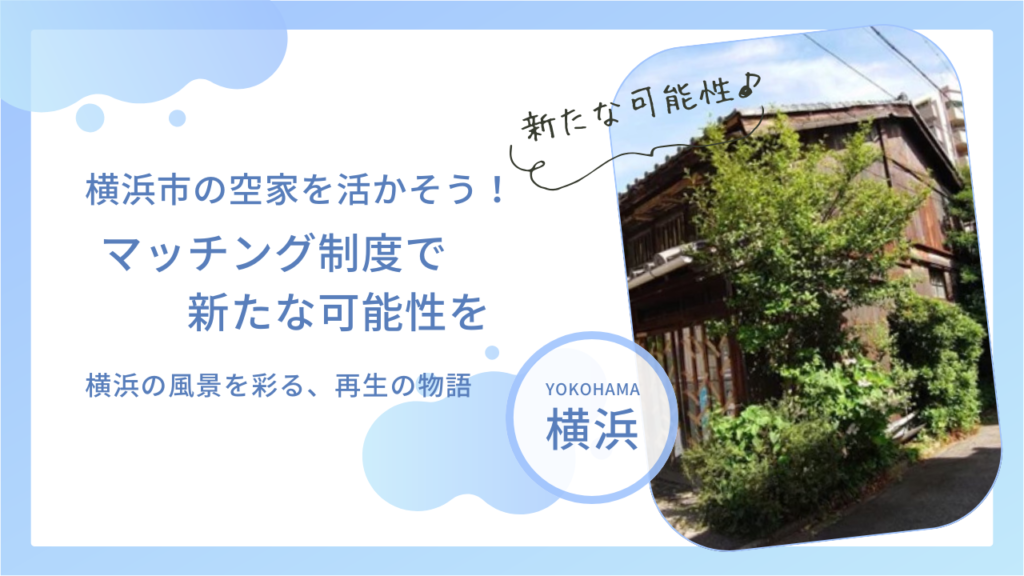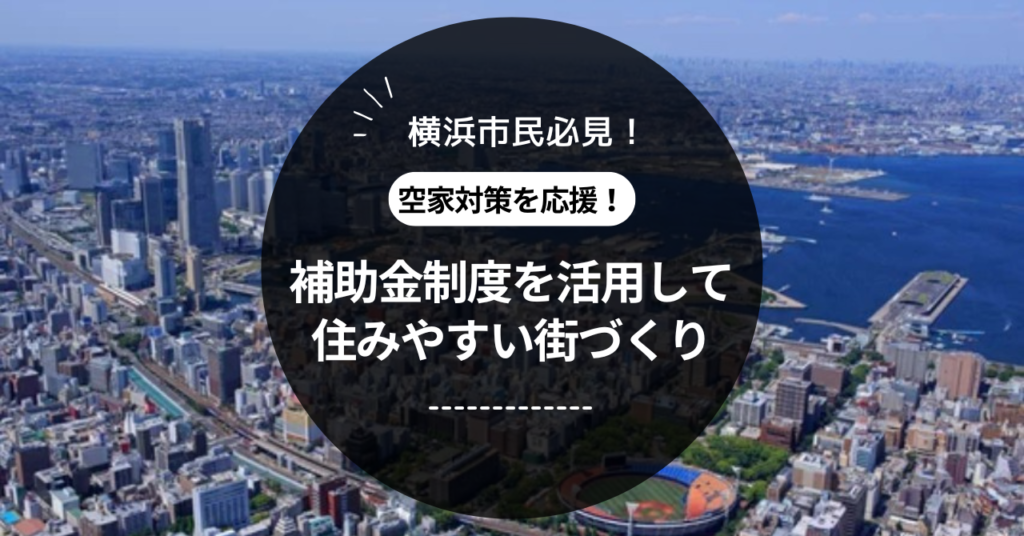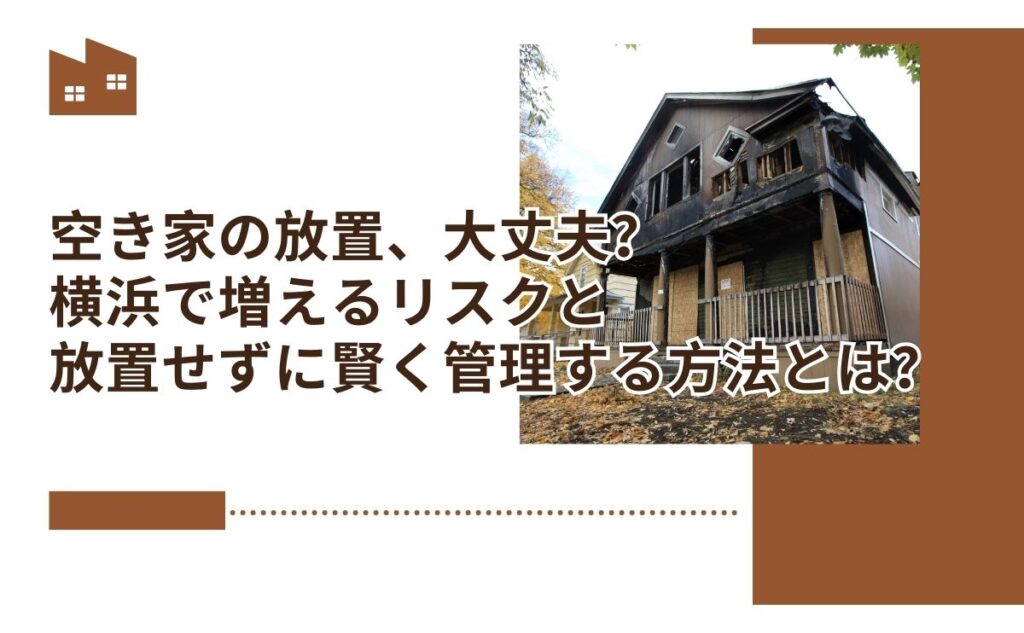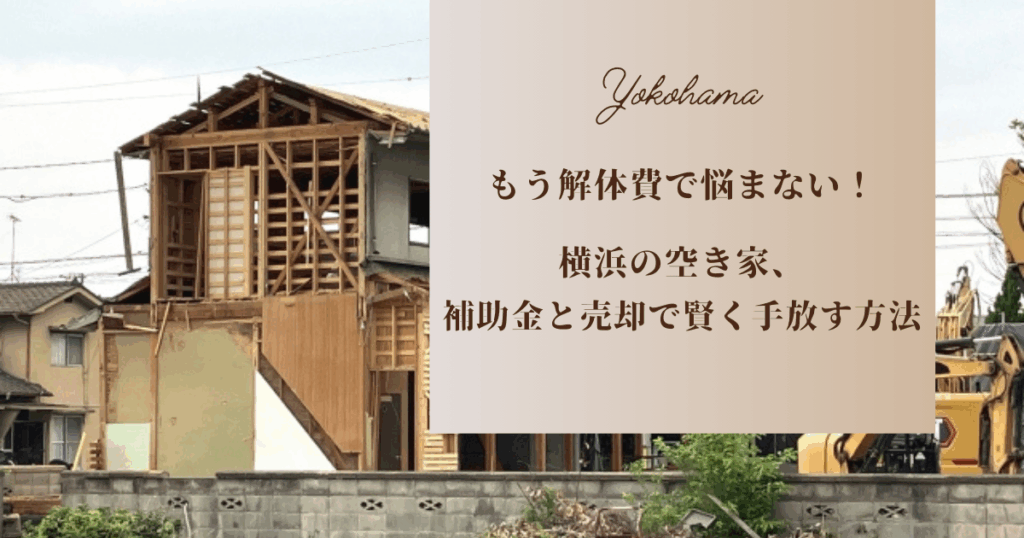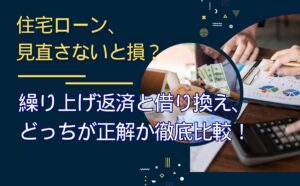横浜で空き家の管理にお困りの方はいらっしゃいませんか?🏡
長年放置された空き家は、倒壊の危険や景観の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。思い切って解体を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、気になるのは解体後の固定資産税ではないでしょうか。
「空き家を解体すると固定資産税が上がる」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
今回は、横浜の不動産事情に詳しい当社が、空き家の解体と固定資産税の関係について詳しく解説いたします。解体を検討されている方はもちろん、空き家問題に関心のある方も、ぜひ最後までお読みください。

なぜ空き家を解体すると固定資産税があがるのか?

なぜ空き家を解体すると固定資産税が上がってしまうのでしょうか?
その最大の理由は、「住宅用地の特例」が適用されなくなるからです。
建物が建っている土地は、「住宅用地の特例」という税制上の優遇措置が適用され、固定資産税が軽減されます。しかし、建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、税額が上がります。
空き家を更地にすると土地にかかる固定資産税は最大6倍、都市計画税は3倍高くなることもあります。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|
| 敷地面積200㎡まで | 評価額 × 1/6 × 1.4% | 評価額 × 1/3 × 0.3% |
| 敷地面積200㎡以上 | 評価額 × 1/3 × 1.4% | 評価額 × 2/3 × 0.3% |
| 更 地 | 課税標準額 × 1.4% | 課税標準額 × 0.3% |
👆上記の表のように、空き家は固定資産税が1/6、または1/3に減額されています。
このように、空き家という「建物」が存在することで適用されていた大きな税制上のメリットが、解体によって失われるため、固定資産税が大幅に上がってしまうというわけです。

ただし、周辺住民や通行人に危害を与える可能性があると判断された空き家は「特定空き家」に指定され、軽減措置特例が適用されない場合があります。
更地にしたら実際にどれくらい固定資産税が上がる?
実際に空き家を解体した場合、固定資産税はどれくらい上がるのでしょうか?具体的な計算例を見てみましょう。
📌例:課税評価額2,500万円(土地)、300万円(建物)の住宅(200㎡以下)があったとします。
※築古の空き家状態で価値が低くなっている家屋を想定しています。
| 🏚 空き家がたっている場合 🏚 |
|---|
| 【土 地】2,500万円 × 1/6 × 1.4% = 5.8万円 【家 屋】300万円 × 1.4% = 4.2万円 合 計:約10万円 |
住宅用地の特例が適用されている場合、土地の課税標準額は評価額の6分の1、つまり約416万円となります。これに固定資産税の税率(例えば1.4%)をかけると、年間の固定資産税は約5.8万円となり、家屋の固定資産税と合計すると、年間約10万円となります。

| 🚧 空き家を解体して更地となった場合 🚧 |
|---|
| 【土 地】2,500万円 × 1.4% = 35万円 |
しかし、この住宅を解体して更地にした場合、住宅用地の特例は適用されなくなり、課税標準額は土地の評価額そのままの2,500万円になります。同じ税率1.4%で計算すると、年間の固定資産税は約35万円にもなるのです。
このように、解体によって固定資産税が大きく跳ね上がってしまうケースも考えられます。この差額は、家計にとって大きな負担となる可能性があります。
ただし、注意しておきたいのは、固定資産税の評価額や税率は、土地の状況や自治体によって異なるという点です。上記の計算例はあくまで一例であり、実際にどれくらいの税額になるかは、お住まいの自治体の税務課に必ず確認することをおすすめします。
また、都市計画税も別途課税される場合があることも覚えておきましょう。
安易な解体は、思わぬ税負担増につながる可能性があることを認識しておきましょう。

特定空き家と固定資産税の新たな問題
「空き家を放置しておくのも問題だし、かといって解体すると税金が上がる…どうすればいいの?」
そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、空き家を放置し続けることにも、新たな問題が生じています。それが、特定空き家への指定です。

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、倒壊の危険性や衛生上の問題、景観の著しい阻害など、周囲に悪影響を及ぼす恐れのある空き家は特定空き家に指定される可能性があります。
これまでは、建物を残していれば住宅用地特例が適用され続けていましたが、特定空き家への勧告を受けると、その恩恵も受けられなくなります。
空き家を放置し続けることは、近隣住民への迷惑だけでなく、所有者自身の経済的負担も増大させることにつながるのです。
固定資産税を抑えるための回避策!
空き家の解体は、固定資産税の増額というリスクを伴うため、慎重な検討が必要です。
しかし、放置し続けることも「特定空き家」への指定や劣化による危険性など、別の問題を生じさせます。では、どのようにすれば固定資産税の負担を抑えつつ、空き家問題を解決できるのでしょうか?
1⃣ 解体以外の選択肢を検討する
✨ 賃貸して再活用
費用はかかりますが、リフォームして住んだり、賃貸物件として貸し出したりすることで、住宅用地特例を維持しつつ収益を得ることも可能です。

💰 売却する
建物付きのまま売却することで、解体費用や解体後の固定資産税増額のリスクを回避できます。築年数が古くても、リノベーション需要などで買い手が見つかる可能性もあります。

🎠 地域活動・コミュニティスペースに転用
地域住民の交流促進や課題解決に貢献し、空き家が社会的な価値を持つ場所として生まれ変わります。地域内外から人が集まることで、新たな交流や活動が生まれる可能性があります。

💻 事業用としての活用
オフィスやコワーキングスペース、シェアアトリエ、スタジオ、教室、小規模店舗(雑貨店、カフェなど)など、事業用に転用することで、安定した賃料収入に加え、地域経済への貢献や新たなコミュニティ形成といった社会的な価値も生み出すことができます。

2⃣ 解体後の土地活用を具体的に計画する
🚙 駐車場として活用
更地にした後、駐車場として活用すれば、収入を得ながら固定資産税の負担を軽減できます。ただし、駐車場にすれば税金が住宅用地特例適用時と同等になるわけではないので注意が必要です。

🏢 アパートやマンションを建設
新たに建物を建築すれば、再び住宅用地特例が適用されます。ただし、多額の初期投資が必要となり、賃貸需要の見極めも重要です。

📦 トランクルームやレンタル倉庫
アパートなどの建設に比べて初期投資を大幅に抑えられ、空き家の解体で更地になった土地を有効活用できます。ただし、駐車場と同様に、住宅用地特例は適用されませんので注意が必要です。

まとめ
空き家問題は、単に「家がある」というだけでなく、固定資産税の負担増、管理の手間、そして近隣トラブルなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。
特に、空き家を解体すると固定資産税が最大6倍に跳ね上がるという事実は、多くの方にとって衝撃的だったかもしれません。
しかし、空き家を放置し続けた結果、「特定空き家」に指定され、建物が残っていても住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が上がるというリスクも存在します。どちらの道を選んでも、税金の問題は避けて通れません。
当社は横浜の不動産事情に精通しており、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。解体後の土地活用、リフォームによる再活用、売却、賃貸、あるいは横浜市が提供する補助金制度の活用など、様々な選択肢の中から、お客様にとって最もメリットのある方法を一緒に見つけ出しましょう。
空き家問題は、早めに専門家へ相談することが解決への第一歩です。ぜひお気軽に、横浜の不動産に詳しい当社にご相談ください。お客様の空き家が、新たな価値を生み出すお手伝いをさせていただきます。
-min.jpg)