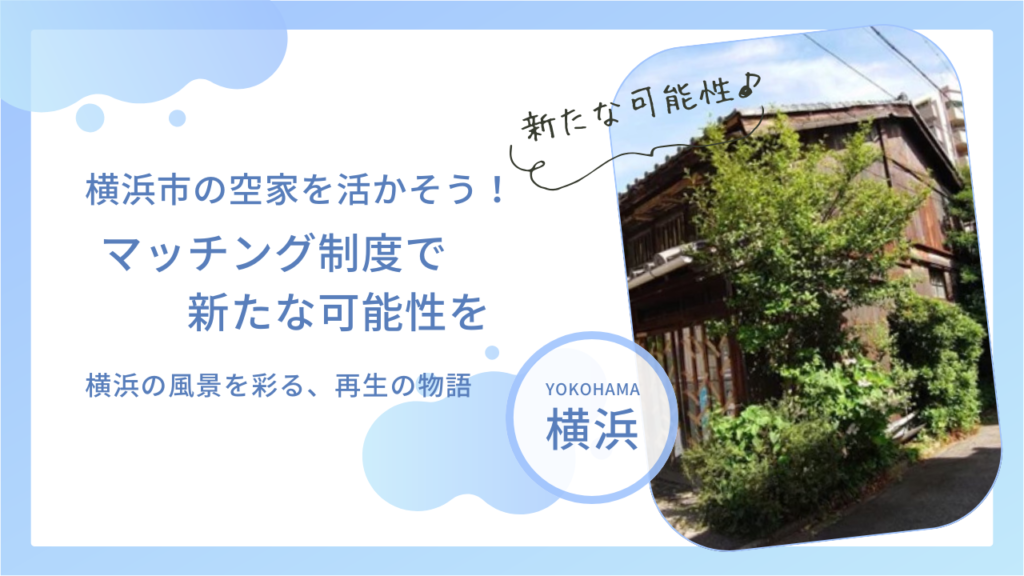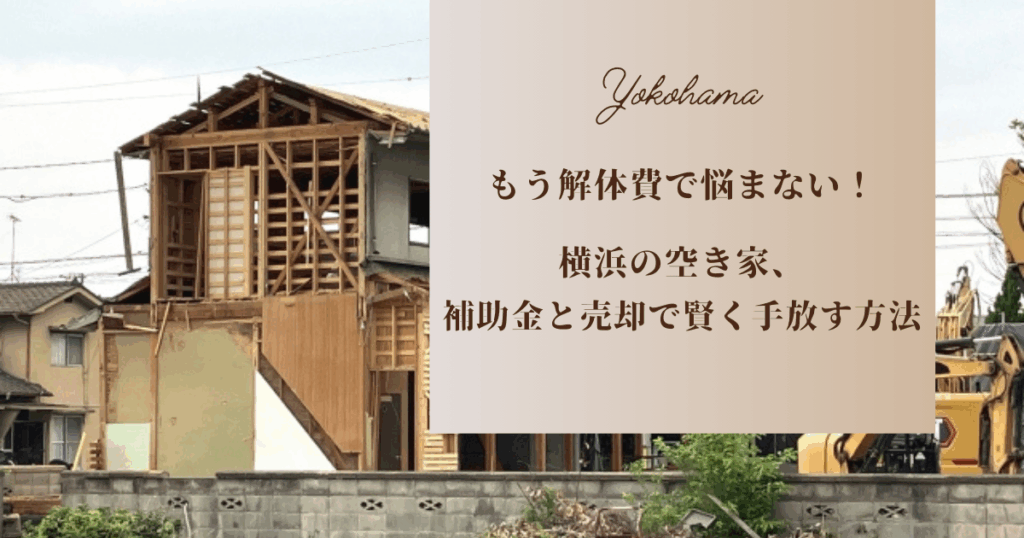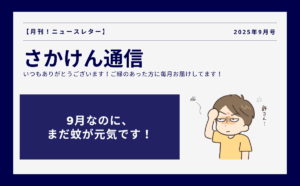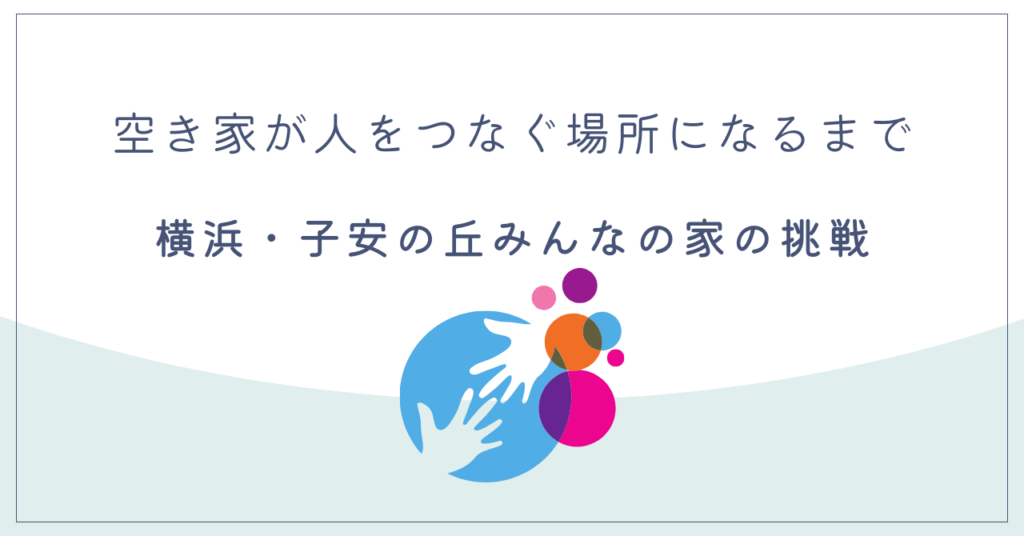
「子安の丘みんなの家」という場所をご存知でしょうか?
JR京浜東北線・新子安駅から歩いて15分ほど。都会の喧騒から少し離れた閑静な住宅街に、ひっそりと佇む築古の一軒家がありました。
その建物の名前こそが、今回ご紹介する「子安の丘みんなの家」です。
もともとは個人の住宅だったこの建物が、リノベーションを経て、地域の人々の交流の場として生まれ変わりました。
「負動産」として放置されていた空き家が、地域の“みんなの家”として再生した、「子安の丘みんなの家」の事例をご紹介します。
子安の丘みんなの家とは?~地域の「使い道」が再生のカギ🗝
横浜市神奈川区・新子安の高台にある住宅地に、築50年あまりの一軒家がありました。
その物件には、いくつものハンデがありました。
🔹 借地権付き(つまり土地は自分のものではない)
🔹 老朽化(建物の痛みが目立つ)
🔹 狭小地(面積が小さく使いにくい)
さらに、
🛤️ 道路には階段を使わないと行けないため、
🚗 車の出入りもできず、
🏗️ 再建築も困難という、
いわゆる“負動産”の典型のような状態でした。
売ることも、貸すことも難しい…。そんな、誰もが持て余してしまうような空き家だったのです。
でも、そんな家に新しい可能性を見出した人たちがいました。
物件を引き継いだ不動産会社が、地域や企業、行政とタッグを組み、空き家を「地域の居場所」として再生するプロジェクトを立ち上げたのです。
その名も――
🏡 「子安の丘 みんなの家」。
この取り組みのユニークな点は、物件の「経済的価値」ではなく、「地域的・社会的価値」に光を当てたこと。
古くて不便でも、そこに人が集まり、笑い声が響き、新たな交流が生まれる。
そんな“居場所”としての家のあり方を、地域ぐるみで築いていくチャレンジです。
地域の“居場所”として生まれ変わった空き家🏠
再生された「子安の丘みんなの家」は、地域の誰もが自由に訪れることができる“ひらかれた居場所”として運営されています。
子育て中の親子がふらっと訪れたり 👨👩👧👦
ご高齢の方々が一緒に昼食を囲んだり 🍱🧓👵
若者たちが小さなイベントを開いたり 🎈🎤
日々さまざまな人が行き交い、自然なかたちで交流が生まれています。
そこにあるのは、ただ「人が人らしく過ごせる場所」🌿──
以前は活用方法もわからず放置されていた空き家が、今では地域のやさしい空気を包み込むような存在になっています。
このプロジェクトでは、収益性を重視した商業施設やレンタルスペースではなく、あくまで“人のつながり”を重視した設計が行われています。
資金面では地元の企業や地域住民の方などからの寄付などが多く集まり、運営は地域のボランティアや住民が協力して行っています。また、横浜市や民間の中間支援団体とも連携しており、空き家の法的整理や改修費用の一部にも支援制度が活用されました。
まさに「地域×企業×行政」の三者協働によって、空き家は新たな地域資源として再生されたのです。
なぜこの空き家は活かせたのか?──成功のポイント🔑
「子安の丘みんなの家」が成功をおさめた背景には、いくつかの大切な要素がありました。
✅ 1. 「利益より地域貢献」を選んだこと
「子安の丘 みんなの家」は、築50年以上・再建築不可という“売れにくい空き家”でした。それでも所有者は、「誰かの役に立つなら活かしたい」と自ら取得。
🛠️ DIYや💰 助成金(横浜市のまち普請事業)を活用し、約1,000万円かかる改修を550万円に抑えて再生。

💡 利益よりも「地域の未来」を優先した選択が、成功の大きなカギになりました。
✅ 2. 地域に“居場所”を求める声があったこと
このエリアには、気軽に集まり自由に過ごせるスペースが少なく、住民には「安心して寄れる場所」のニーズがありました。
そこに現れたのが「みんなの家」。
2022年のオープン以降、☕ カフェや🍽 家族食堂、イベントスペースとして、子どもから高齢者までが自然と集まる場に。

そこで、この空き家が持つ「空間」が、
🌟 「人が集まりたい」という地域の想いとうまく重なり合ったのです。
✅ 3. 専門的な支援パートナーの存在
借地権付き・老朽化・再建築不可…。
一般的には活用が難しい物件にもかかわらず、
🏢 地元企業や、🤝 中間支援団体が協力したことで、改修や運営が現実のものとなりました。

🛠️ 専門知識と経験を持つパートナーの存在が、プロジェクトの大きな推進力となったのです。
💬 “売る”でも“貸す”でもない。
あなたの空き家にも、“活かす”という選択肢があります。
空き家をどうにかしたいと思ったとき、つい「売却」や「賃貸」ばかりに目が向いてしまいがちです。
ですが、「子安の丘みんなの家」が教えてくれるのは、
🏡 “人のつながり”に価値を見出す第三の道があるということ。
あなたの空き家にも、まだ見ぬ可能性が眠っているかもしれません。
あなたの空き家も“居場所”になるかもしれない🤝

相続した空き家が「売れない」「貸せない」「使えない」──そう感じて、つい放置を選んでしまう方も少なくありません。
しかし、それは「価値がない」のではなく、“どう活かせばいいか”を知らないだけかもしれません。
今、多くの自治体やNPOでは、空き家活用の相談窓口が設けられています。
横浜市でも、空き家のマッチング制度や、改修・解体に対する補助金制度が整っており、「誰かの手に活かしてもらう」道筋は十分にあります。
もし、あなたの空き家が「どうにもならない」と感じているなら、一度立ち止まってみてください。
その空き家が、地域の子どもたちにとっての遊び場になったり、高齢者にとっての居場所になったりするかもしれません。
「子安の丘みんなの家」は、誰にでもできる“空き家の未来づくり”の第一歩を教えてくれます。
まとめ
相続した空き家を「放置するしかない」と思い込んでいませんか?
確かに、再建築不可・借地・老朽化といった条件が揃うと、売却も賃貸も難しく、どう活かせばいいのか分からないと感じるのは当然です。
しかし、横浜市新子安の「子安の丘みんなの家」のように、地域の課題と結びつくことで、空き家は“人をつなぐ居場所”へと変わる可能性があります。
この事例が教えてくれるのは、空き家の価値は「不動産価格」だけではないということ。
地域との対話や、中間支援団体との連携によって、空き家は“課題”ではなく、“資源”として活かされていきます。
「誰かが住む家」ではなくてもいい。
子どもが遊び、高齢者が集い、誰もがふらっと立ち寄れる。そんな“居場所”としての未来が、空き家には眠っているのです。
放置ではなく、可能性に目を向ける選択を。あなたの空き家にも、まだ見ぬ役割があるかもしれません。
-min.jpg)