
🟢 介護は突然訪れる
いつかは介護することになるだろうとは思っていましたが、それがこんなにも突然訪れるとは思いもしませんでした。
ある日、母が「腰が痛い」と言い出しました。
もともと一人暮らしをしていた母ですが、それまでは特に大きな病気もなく、自分のことは自分でできる人でした。
最初は年齢に伴う「軽い腰痛かな?」くらいに思っていたのですが、痛みが引く気配がありません。
病院で診てもらうと、診断は脊柱管狭窄症。
これまで特に大きな病気をしたことがなかった母にとっても、私にとっても青天の霹靂でした。
💡 手術を決断するまで
年齢のこともあり、手術はできるだけ避けたかったのですが、痛みが強くなり、日常生活にも支障をきたすように。
医師と相談し、最終的に手術を受けることになりました。

術後の生活と不便さ
手術自体は無事に終わり、母は2週間ほどで退院でき、家に戻って療養しました。
🛠 退院後の生活サポート
退院後1ヶ月間は、私が実家に戻り、食事の支度や洗濯、掃除といった家事を担いながら、母の日常生活をサポートしていました。
しかし、腰の病気の影響で、以下のような不便がありました。
| ・一人でズボンや靴下を履くことができない ・床に落ちた物を拾うのが難しい ・重いものを持つことが困難 |
こうした不便さが多く、今後一人での生活は厳しいと感じました。

そこで、夫に相談し、母を同居させてもらうことに。
このとき、私自身も「これからの生活はどうなるんだろう?」「介護なんてできるのか?」と不安を感じましたが、 不安を抱えつつも、できることから始めようと考えました。
介護認定と手続き
次に考えなければならないのが「介護認定」です。
介護認定を受けることで、介護保険サービスを利用できるようになります。
💡 介護サービスとは
介護サービスとは、40歳以上の方が加入する介護保険制度を利用して受けられる公的サービスのことです。
主に65歳以上の方、または40歳から64歳で特定疾病により介護が必要な方で、「要支援1、2」または「要介護1~5」の認定を受けた人が利用できます。
これらの認定区分を重度の順に並べると以下のようになります。
📁 介護認定の区分と支援の目安
| 認定区分 | 介護の必要度 |
|---|---|
| 要介護5(最も重度) | ほぼ全介助が必要 |
| 要介護4 | ほぼ全面的な介助が必要 |
| 要介護3 | 身体介助が頻繁に必要 |
| 要介護2 | 部分的な介助が必要 |
| 要介護1 | 軽度の介助が必要 |
| 要支援2 | 生活機能の低下が見られる |
| 要支援1(最も軽度) | 軽い支援が必要 |
この順序は、介護が必要な度合いを示しており、要介護5が最も介護を必要とする状態で、要支援1が最も軽い状態です。
各段階で必要とされる介護の時間や支援の程度が異なり、要介護度が上がるにつれて、より多くの介護サービスや支援が必要となります。

📁介護サービスの種類と特徴
介護サービスは大きく3つに分類されます。
| サービス種別 | 内 容 |
|---|---|
| 居宅サービス | 自宅で生活しながら受けられる支援 |
| 施設サービス | 特別養護老人ホームなどの施設で受けられる支援 |
| 地域密着型サービス | 住み慣れた地域で継続的に生活できるよう支援するサービス |
これらのサービスは、利用者の状態や必要に応じて組み合わせて提供され、費用の約8~9割が介護保険で賄われます。
📌 介護認定を受けるきっかけ
実際に介護をするようになったとき、介護をどのようにすればいいのか分からず戸惑っていました。そんな中、近所の人が「介護認定を申請するといいよ」と紹介してくれたことをきっかけに、手続きを進めることにしました。
介護認定を受ける際、どのくらいの料金がかかるのかも気になるところです。
申請自体は無料ですが、サービスを利用する際には費用が発生します。
介護サービスの利用費は、要支援や要介護の度合いによって異なり、基本的に自己負担は1~3割程度です。
ただし、所得によって負担割合が変わるため、詳細は市区町村の窓口で確認する必要があります。
📝 介護認定の流れ
申請から認定までの流れは以下のようなものでした。
| 手続き | 内 容 |
|---|---|
| 1. 市区町村の窓口で申請 | 介護保険の申請を行う |
| 2. 訪問調査を受ける | ケアマネージャーや専門員が自宅や病院を訪問し、状況をチェック |
| 3. 審査の結果通知 | 要支援・要介護度が決定される |
| 4. ケアプランの作成 | 介護サービスを利用するためのプランを立案 |
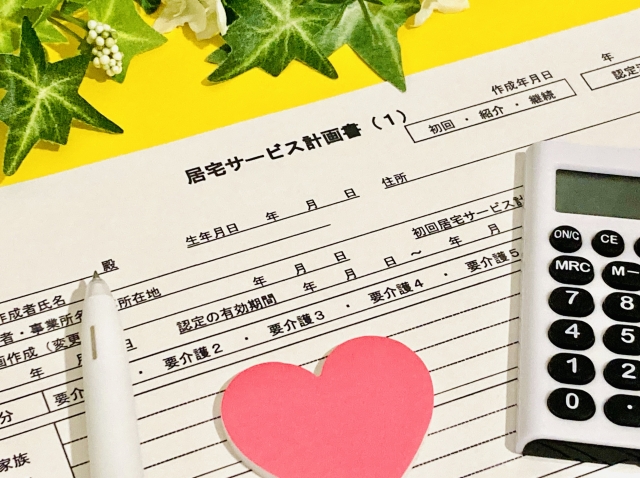
申請から結果が出るまでに1ヶ月ほどかかり、思った以上に時間がかかるものだと実感しました。
母の場合は「要支援2」という結果になり、横浜市で利用できるサービスの中で、デイサービスと介護ベッド、トイレや浴室の手すりなど、福祉用具のレンタルを利用することにしました。
突然のことだったので、何から手をつけていいのかわからず、最初は右往左往していました。
📌 介護で困ったときは
まずは地域包括支援センターに相談するのが良いでしょう。
地域包括支援センターでは、介護認定の手続きや利用できるサービスについてアドバイスを受けることができます。
その後、役所の窓口や地域包括支援センターの相談員の方に助けてもらいながら、少しずつ手続きを進めました。
仕事と介護の両立の難しさ
私自身、仕事を持っているため、介護と両立することの大変さも痛感しました。
母の体調の変化に気を配りながら、仕事のスケジュールを調整したり、仕事仲間に迷惑をかけてしまうこともありました。
特に、介護が突然始まり、コツをつかむまで余裕がなく、試行錯誤の連続でした。
🔍 介護と仕事の両立のコツ
しかし、すべてを自分一人で抱え込まず、
| ・使えるサービスを積極的に活用する(デイサービスや訪問介護など) ・周囲の人に協力を求める(夫や兄弟、親戚と分担と分担) |
といったことを意識することで、少しずつ生活のリズムがつかめるようになりました。

介護は誰にでも突然やってくる!
「介護はまだ先のこと」と思っていても、実際にはある日突然始まるものです。
私自身、もっと事前に知っておけばよかったと思うことがたくさんありました。
📌 介護に備えてできること
これから介護に直面する可能性のある方へ、私が感じた準備すべきことをまとめます。
| ・親の健康状態を日頃から把握しておく(気になる症状があれば早めに検査) ・介護認定の仕組みを知っておく(手続きには時間がかかるため、早めに相談) ・家族と介護について話し合っておく(いざという時にスムーズに決断できる) ・仕事と介護の両立を考え、使える制度を調べておく(介護休業制度、在宅ワークの可能性など) |
まだまだ試行錯誤の毎日ですが、少しでもこれから介護に向き合う方の参考になればと思います。
次回の記事では、『実家じまい』についてお話ししたいと思います。
介護のために同居することになり、急に訪れた実家じまい。
実家の整理や片付けに直面したときに感じたことや、進め方のポイントをお伝えします。
少しでもこの記事が、皆さんのお役に立てば嬉しいです。
-min.jpg)


